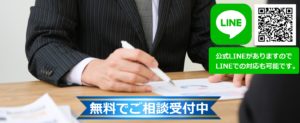あ行
・後飾り(あとかざり)
「中陰飾り(ちゅういんかざり)」とも言い、葬儀が終わり帰宅した後にお骨・お位牌・遺影写真などを忌明け(四十九日)まで飾り、供養することをいいます。飾るための祭壇を「中陰段(ちゅういんだん)」「後飾り祭壇」といいます。
・阿弥陀仏(あみだぶつ)
「阿弥陀如来(にょらい)」「阿弥陀さん」とも呼ばれていて、極楽浄土へと導いてくれる仏様になります。浄土宗・浄土真宗においての御本尊になります。「南無阿弥陀仏」は六字名号や念仏と呼ばれます。
・一日葬(いちにちそう)
お通夜式を行わず、当日に家族以外の参列者や宗教者(お寺さま)に来てもらい、葬儀告別式のみ行う形式になります。昨今では心身の負担の軽減や費用を抑えることができるため増加傾向にあります。
・一膳飯(いちぜんめし)
故人様の枕元に施す枕飾りで、お茶碗にご飯を山盛りにしお箸を立てたものをさします。枕飯(まくらめし)・一合飯(いちごうめし)・お仏飯(おぶっぱん)とも呼ばれ、宗教・宗派によってお箸を立てない場合もあります。
・打敷き(うちしき)
仏壇や経机に使用する四角形や三角形の敷物になり、その上に仏具などを安置します。色は赤や紫・金色などで金襴を使用されているため派手なものが多いのですが、不幸があれば忌明け(四十九日)まで白色のものを使用します。仏壇に付属している打ち敷きは裏側が白になってることが多いです。
・盂蘭盆(うらぼん)
旧暦(太陰暦)においてのお盆をいい、期間は7月13日~16日の四日間をさしています。盂蘭盆に行う法要を盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。関西地方ではお盆は8月ですが、関東地方や北海道地方の一部では7月に行われています。
・エンディングノート
自身が万が一のときに、さまざまな希望や家族に知ってもらいたいことを記すノートです。書くことにより、お葬式や葬儀後の手続きなどでの判断材料となり、ご家族の心身の負担を軽減できたり希望通りのお葬式を行ってもらうことができます。またノートを書くことにより、今まで話せなかったことなどを話すきっかけになったりもします。
・永代供養(えいたいくよう)
永代に渡って霊園や寺院がご遺骨を管理・供養してくれる埋葬の方法をいいます。お墓を持たない方、お墓参りに行けない方、事情があり墓じまいをしなければいけない方、お墓を購入するより費用が安いという方などが利用されており、年々増加傾向にあります。
・御布施(おふせ)
宗教者(お寺さま)に葬儀や法事をおつとめ頂いたお礼として現金を不祝儀袋に入れてお渡しするものとなります。相場は地域や宗教者によって異なりますので、直接付き合いのあるお寺さまへご確認下さい。当社紹介の宗教者であれば、¥50,000より手配いたします。
か行
・戒名(かいみょう)
仏の世界での名前になります。本来は、仏教教団に入り(出家)戒律を守ることを誓った者だけに与えられる名前でしたが、昨今では亡くなった際に戒名を与えることが一般的になっています。宗教・宗派によって「法名(ほうみょう)」「法号(ほうごう)」と呼ばれたりします。浄土真宗では法名といいます。
・忌中(きちゅう)
不幸があってから四十九日法要までの期間、神式の場合は五十日祭までの期間を忌中といいます。四十九日もしくは五十日を過ぎると忌明けとなります。
・供花(くげ)
または供花(きょうか)と読みます。お花を供えるという意味で、お葬式や法要の際、故人様やご先祖様にお供えする盛花になります。仏壇やお墓に供える仏花とはまた違います。
・献花(けんか)
キリスト教や無宗教(自由葬)など焼香を行わない場合、お花を献花台へと献上するお作法になります。お花の種類は白いカーネーションや菊、白のユリなどで行うことが多いです。しかし昨今では、故人様の好きだった花(赤いバラ、トルコ桔梗、胡蝶蘭など)で行われる形式も増えて来ています。
・香奠・香典(こうでん)
お葬式の際、お香料やお花の代わり、またはお悔やみの気持ちを込めて当家に現金をお渡しする儀式になります。宗教・宗派によって「御霊前(ごれいぜん)」「御仏前(ごぶつぜん)」「御玉串料(おたまぐしりょう)」「御献花料(ごけんかりょう)」など使い分けはさまざまです。不祝儀袋への表書きは「御香奠(おこうでん)」が正式な書き方ですが「御香典」でも問題ありません。
さ行
・逆さごと(さかさごと)
この世とあの世では逆の世界となるため、それを分け隔てるために行われている風習になります。この世で通常行うことを逆の方法で行えば魂が死を悟り、未練を残さずに成仏が出来るという考えです。例えばご飯にお箸を立てる、枕元の屏風を上下逆に設置する、着物の前合わせを右前から左前にするなど、さまざまな風習があります。湯灌(ゆかん)の際に逆さ水を行いますが、こちらも逆さごとになります。
・死化粧(しにげしょう・しげしょう)
故人様の髭を剃り、故人様らしい姿にするために施すメイクとなります。男性の場合は髭を剃ることをメインとし、濃い化粧などは行いません。また、脱脂綿により口・鼻・耳からの体液の滲出(しんしゅつ)を防ぎ、遺体に対しての尊厳を守ります。
・頭北面西右脇臥(ずほくめんさいうきょうが)
お釈迦様が亡くなられた際、頭を北に・顔を西に・右脇を下にして寝ていたとされています。「北枕(きたまくら)は縁起が悪い」といわれる理由でもあります。しかし、風水では北枕(北の方向)が非常に良い方角とされていて、あえて北枕で寝る方も多くいらっしゃいます。
・生前予約(せいぜんよやく)
生前葬儀の内容を具体的に取り決め、予約・契約することをいいます。葬儀社が決まっていることが前提となりますので、自身に合った信頼できる葬儀社を選ぶことが重要です。生前に死後を決めるのは縁起が悪いともいわれますが、昨今では終活の一環として需要が増えて来ています。
・粗供養品(そくようひん)
通夜式・葬儀告別式に参列して頂いた方にお渡しする品物をいいます。両日に参列される方もいらっしゃいますので、通夜式と告別式でお品を変えるのが一般的です。品物は、お茶やコーヒー・お菓子やタオル・ハンカチや石鹸などが多く、それぞれの金額の相場は500円~1000円程度になります。
た行
・玉串奉奠(たまぐしほうてん)
神道(神式)では焼香ではなく、榊(さかき)に紙垂(しで)と呼ばれる紙を付けた玉串を、玉串案(たまぐしあん)と呼ばれる机に献上します。こちらのお作法を玉串奉奠といい、神社神道・天理教・金光教・黒住教など神式でのお作法になります。
・中陰・中有(ちゅういん・ちゅうう)
命日から四十九日までの期間を中陰または中有といいます。また、その期間に位牌やお骨・遺影写真を飾ることを「中陰飾り」または「後飾り(あとかざり)」といいます。
・通夜振舞い(つやふるまい・つやぶるまい)
通夜式が終わり参列のご遺族・ご親戚を会食室へ招き、食事を振る舞うことをいいます。本来であれば精進料理でひっそりと行うのですが、昨今では桶で用意したお寿司やオードブルなどで手軽につまめ故人を偲び、思い出話で盛り上がれるような食事形態になっています。
・手元供養(てもとくよう)
手元(身近)に故人様の遺骨を置いて供養することをいいます。お墓を建てなかったり、お墓が遠くなかなかお墓参りに行けなかったり、大切な人を遺骨と共に過ごしたいという方が遺骨をアクセサリー(ペンダント・ブレスレット・ブローチ・リング(指輪)など)に加工し手元に置いて供養することをいいます。
・友引(ともびき)
世間では「友引にお葬式をしてはいけない」「友引は友(身近な人)を引く(あの世へ連れて行く)」と言われていますが、本来の意味は中国の運勢などを表す「六曜(ろくよう」という占いになります。カレンダーに記載されている先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口がそれにあたります。もともと六曜と仏教・葬儀には何の関係も無かったのですが、いつの日にか日本の文化に浸透してきました。
な行
・南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)
六字名号(ろくじみょうごう)や念仏ともいい、インドのサンスクリット語「ナマステ」という言葉からきています。ナマスは南無となり「礼拝・敬礼・おじぎ・あいさつ・服従」などの意味があります。テはあなたにという意味になりますが、阿弥陀は「アミターバ(無量の光明)」「アミターユス(無量の寿命)」ということから「阿弥陀仏に帰依(礼拝)します。」という意味になります。浄土真宗本願寺派(西)では「なもあみだぶつ」と発音します。
・新盆(にいぼん・あらぼん)
初盆(はつぼん)ともいい、亡くなられて初めて迎えるお盆のことをいいます。初めて迎えるお盆ということで、お供え物や灯明など通常のお盆よりも手厚く供養するのが一般的で、初盆だけはお寺さまにお参りしてもらうという方も多くいらっしゃいます。
・塗り位牌(ぬりいはい)
本位牌(ほんいはい)ともいいます。四十九日法要が終えた後、白木の仮位牌から漆塗りで金箔の装飾を施した位牌に変えて仏壇に安置します。
・念仏(ねんぶつ)
浄土宗や浄土真宗など浄土教において合掌礼拝する際、「南無阿弥陀仏」と称えることをいいます。
・納棺(のうかん)
故人様をお棺に納める事をいいます。身体に処置を施し旅支度を整えてから入棺し、副葬品を納める儀式です。
は行
・花祭壇(はなさいだん)
生花祭壇(せいかさいだん)ともいい昨今では使い回しの白木祭壇が減少しており、花祭壇が主流になっています。故人様が好きだったお花を装飾することもできます。
・百か日・百箇日(ひゃっかにち)
故人様が亡くなられてから百日目をさします。この日に法事を行うことを百か日法要といいます。
・袱紗(ふくさ)
葬儀など弔事やお祝い事の慶事の際、現金を渡す場合に使用するものとなります。漢字が「袱紗」「服紗」「帛紗」とありますが、「袱紗」は金品を包むもの、「服紗」や「帛紗」は茶道において茶道具を拭き清めたり、お茶碗やその他の茶道具を拝見するときに使用します。
・変動費用(へんどうひよう)
葬儀の費用の中で、食事代・宗教者へのお礼・参列者への返礼品など人数などによって変動する費用をいいます。
・法号(ほうごう)
仏の世界での名前になり、日蓮宗ではそれを法号といいます。昨今では亡くなった際に戒名を与えることが一般的で、宗教・宗派によって「戒名(かいみょう)」「法名(ほうみょう)」と呼ばれたりします。
ま行
・枕飾り(まくらかざり)
仏式の葬儀の際、故人様の枕もとに白木の経机を準備し、三具足(香炉・燭台・花立て)・ご飯(一膳飯)・枕団子・お水などを安置し飾り付けを行いますが、こちらを枕飾りといいます。お葬式までの間、ご家族やご親戚でお線香を絶やさず、故人様の魂が迷わずに成仏できるよう供養するという意味があります。
・名号(みょうごう)
仏様や菩薩様の名前をいいます。「阿弥陀仏」や「釈迦牟尼仏」などがそれにあたります。また南無阿弥陀仏は六字名号・南無釈迦牟尼仏は釈迦名号・南無大師遍照金剛は弘法名号といいます。
・無宗教(むしゅうきょう)
仏教や神道・キリスト教など決まった宗教・宗派を信仰されていないことをいいます。また、お葬式では決まった形式が無いため無宗教葬や自由葬と呼ばれています。宗教者を呼ばない直葬や火葬式は無宗教葬や自由葬とは言わず、葬儀の形式をさします。
・冥土(めいど)
「冥途」とも書きます。「あの世」や「冥界」「黄泉(よみ)」も類語になり霊魂が行く世界で、特にこの世で悪い行い(罪)を犯した者がたどり着く地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道をさしています。「冥土の土産」とは、あの世に行く人の思い出話や自慢話、晩年にお願いを叶えてあげたり(旅行など)し、安心して成仏する・してもらうための喜ばしい事柄をいいます。
・喪主(もしゅ)
喪主とはご遺族の中の誰かが行うもので、主にお葬式の内容を取り決めたり、参列者や宗教者への対応など重要な役割の方をさします。故人の配偶者や長男が喪主を務めることが一般的です。
や行
・矢筈(やはず)
掛け軸をかける際に使用する棒状の道具になります。
・湯灌(ゆかん)
桶やタライに溜めたお湯で全身を洗い清める儀式になります。湯灌の儀式は約1300年も前から行われていたとされ、死者の魂を浄化する・宗教儀式の中のお作法・身体の汚れを落とすなど、物理的や宗教上の理由から湯灌の儀式が生まれたとされています。
・黄泉(よみ)
黄泉の国ともいわれます。霊魂が行く世界になります。黄泉=地獄のイメージがありますが、そうではなく黄泉は神道で地獄は仏教になり、それぞれ別の世界です。
ら行
・臨終(りんじゅう)
亡くなった時のイメージがあり、死の直後に「ご臨終です」という言葉も良く耳にしますが、本来は亡くなる間際のことを意味します。臨命終時(りんみょうしゅうじ)を略した言葉になります。
・霊柩車(れいきゅうしゃ)
ご遺体を搬送する貨物車両になります。国土交通省に認可を得ている緑ナンバー車(営業用車)で、白ナンバーでご遺体を搬送し料金をもらう行為は違法になります。昨今では地車(だんじり)の屋根が付いたみたいな「宮型霊柩」の需要が減りステーションワゴンを改造する「洋型霊柩車(リムジン型)」と呼ばれる車両が主流になっています。他にも「バン型霊柩車」や「バス型霊柩車」などもあります。病院や施設から安置場所まで運ぶ車両を「寝台車(しんだいしゃ)」と呼ばれています。
・六文銭(ろくもんせん)
仏教の世界のもので、三途の川の渡し賃といわれています。三途の川とは現世と死後の世界を隔てている川で、渡し船で川を渡るための料金が六文となります。「六道銭(ろくどうせん)」や六連銭(ろくれんせん)と呼ばれることもあります。また有名な武将の真田幸村など真田家の家紋が六文銭で「真田銭(さなだせん)」といいます。
わ行
・別れ花(わかればな)
納棺の際や斎場への出棺前にご遺族・参列者が故人様にたむけるお花をいいます。お花の種類に特に決まりが無く、菊などの和花やユリやカーネーションなどの洋花・故人様が好きだったお花でお別れを行うことが主流になっています。薔薇などトゲのあるお花は避けられていましたが、昨今では故人様が好きであれば問題ないという理由でトゲを取って納める方も増えています。