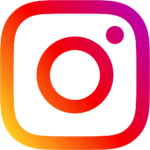一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
はじめに
葬儀で着用する服装を喪服といいますが、種類はいくつかあり男性・女性・お子様によって服装が違いマナーがあります。
昨今では親類のみの家族葬の増加により、葬儀での正しい服装のマナーを知るという意識が薄れていたり、時代の流れとともに通夜式と葬儀式での服装のマナーが昔に比べ変化しているともいえます。
「参列者を親族のみに限定した家族葬では、そこまできちんとした服装でなくてもいい」という考え方になってしまうのは仕方がないとはいえますが、きちんとした喪服を着用しないといけないシーンが訪れるかもしれません。
こちらでは本来お葬式で何を着るのか?お葬式での服装や装飾品などのマナーについてご紹介させて頂きます。
合わせて喪服を持っていない場合「購入がいいのか?」「レンタルがいいのか?」についてもご案内いたします。
喪服とは
喪服の読み方は「もふく」です。
「礼服(れいふく)」という言葉も聞いたことがあると思いますが、礼服とは冠婚葬祭で着用する正装(フォーマルウェア)をいいます。
喪服の喪には「親族や親戚の死後に一定期間、家にこもってつつしむ」という意味があり、このことから喪服は葬儀や法要などの弔事や仏事で着用する服をさします。
すなわち礼服という服の中に喪服があるということになります。
また、喪服には「略喪服」「準喪服」「正喪服」の3種類があり、着用する方の立場や弔事のシーンによって異なります。
喪服と仕事などで着用するダークスーツ(略礼装)との違いは色の黒さが全然違います。生地の染め方が違い、喪服は生地に光沢感が無くマットな仕上がりのものになります。喪服と黒系のダークスーツを比べて見ると生地の黒さの違いが一目で分かります。
デザインの違いでいえば、
- 襟の部分にステッチが入っていない
- 腰部分の切れ目(ベント)が入っていない
などがあげられます。
女性の喪服のマナーについて

| 洋装の正喪服 |
| 最も格式が高い喪服となり、光沢感のない黒無地のワンピース・アンサンブル・スーツなどのブラックフォーマルが該当し、パンツスーツは正喪服に入らないというのが一般的な認識です。正喪服は通夜式や告別式において喪主様・ご遺族・ご親族が着用するものとなります。フォーマルドレスは装飾の少ないシンプルなデザインが望ましく、袖は長袖か七分袖、スカートは膝丈より下がよいでしょう。パンプスはヒールが低く装飾や金具のないものをご用意しましょう。 |
| ★洋装の準喪服 |
| 正喪服の次に格式の高い喪服となり、昨今ではお葬式や法事で1番着用される喪服です。女性の場合はワンピース・アンサンブル・スーツなどのブラックフォーマルが該当し、正喪服とほぼ同じです。一般的に喪服と言えばこの準喪服にあたり、昨今では喪主様から参列者まで幅広く着用されています。フォーマルドレスはフリルやリボンなど控えめな装飾があってもよく袖は長袖~五分袖、スカートは膝丈より下がよいでしょう。パンプスはヒールが低く派手な装飾や金具のないものが望ましいです。 |

| 洋装の略喪服 |
| 準喪服より格式が低いの喪服となり、ブラックフォーマル以外の黒・紺・グレーなどの地味な色合いでシンプルなデザインのワンピース・スーツなどに当たります。急な訃報で準喪服が準備出来ない場合に通夜式や告別式・ご自宅などに駆けつける時に着用します。洋服は目立たない柄でカジュアル過ぎないものであればよいでしょう。インナーのシャツやブラウスは白を避け地味な色合いにし、パンプスはヒールが低く装飾や金具のないものをご準備しましょう。 家族葬だからといって喪服を所持しているのに、略喪服を着用していくのは極力避けた方がよいといえます。 |

| 和装の正喪服 |
| 着物を着用する場合は、黒無地の染め抜き五つ紋付の着物が正式な喪服となります。家紋は嫁ぎ先の紋・実家の紋を入れるのが一般的で、帯は黒無地または黒の紋織を締めます。足袋は白で草履は黒の布製が正式ですが、革性でも光沢がないものであればよいでしょう。 |
| 和装の略喪服 |
| 靴や草履は正式には黒色で布製となりますが、光沢のない革やフェイクレザー製でも大丈夫です。ヒールのない靴はカジュアルな印象があるので極力避け、派手な装飾や金具がなくヒールが低くシンプルなパンプスを選びましょう。 |
装飾品・アクセサリーについて
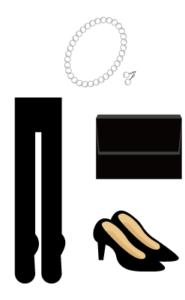
| ヘアスタイル | ロングヘアーの場合は一つ結びやお団子など、すっきりシンプルにまとめるのがよいでしょう。昨今では編み込みなどファッション性のある髪型で参列される方も多いのですが、あえて派手で目立つ髪型にする必要はないといえます。 |
| お化粧 | アイメイクやチーク・口紅は派手なものを避け、ナチュラルなメイクを心がけましょう。 |
| ネイル | マニキュアやジェルネイルは基本的にはしていない状態が望ましいのですが、難しい場合は手袋や肌色などのネイルカラーを重ねるなど目立たないように心がけるのがマナーといえます。 |
| 靴 | 靴や草履は正式には黒色で布製となりますが、光沢のない革やフェイクレザー製でも大丈夫です。ヒールのない靴はカジュアルな印象があるので極力避け、派手な装飾や金具がなくヒールのあるシンプルなパンプスを選びましょう。 |
| バッグ | バッグはショルダーではなく手提げタイプで、素材は布製が正式ですが革やフェイクレザー製でも装飾が少なくシンプルで光沢のないものであればよいでしょう。 |
| ストッキング | 黒で柄がないストッキングを履きましょう。タイツはカジュアルな印象があるので極力避けた方がよいです。 |
| アクセサリー | 本来は結婚指輪以外のアクセサリーは控えるのが正式ですが、昨今ではアクセサリーがあって正式という考え方もあります。しかしダイヤモンドや宝石などのキラキラし過ぎたジュエリーなど光物は避けましょう。着用するのであれば、黒や白の真珠のネックレス(一連)・イヤリングなどがよいです。二連や三連のネックレスは不幸が重なるなどの忌み(いみ)的な意味合いがあるので避けるべきです。 |
弔事でのネイルのマナーはこちらをご覧下さい。

2024.03.04
葬儀にネイルやマニキュアはダメ?隠し方や対処法をご紹介
葬儀の参列にネイルやマニキュアはマナー違反!? コチラのページにも簡単に書かせていただいていますが、昨今では若い・年配に関わらず女性の方は爪...
男性の喪服のマナーについて

| モーニングコート(正喪服) |
| モーニングコートは男性の洋装で1番格式が高く、名前の通り夜間(通夜式)に着用することはありません。黒とグレーの縦縞のズボンとベストを着用します。昨今では参列の方が多い一般葬や社葬にて着用する場合が多く、家族葬では準喪服や略喪服を着用される方がほとんどです。 |

| ★準喪服 | |
| シングル | シングルスーツは前のボタンが1列で2つ~3つボタンのものが主流で、白のYシャツ・黒のネクタイを着用します。男性がお葬式で着用されることが1番多い装いとなり、喪主様からご親戚まで、そして通夜式から告別式と幅広く着用する事ができます。靴は装飾が無くシンプルで黒のものをご準備しましょう。 |
| ダブル | ダブルスーツは、前のボタンが2列で4つボタン・6つボタンのものが主流で、白のYシャツ黒のネクタイを着用します。カフスボタンを付けるときは光物は避け地味なものを選びましょう。 |
| 違い | シングルスーツは若い方が着用するもので格式が低い、ダブルスーツは年配の方が着用し格式が高いというイメージをお持ちの方がたくさんいらっしゃいますが、格式や年齢などの違いはありません。結論的には好みや流行の違いであり、年配の方がダブルを着用してるのを良く見たり、シングルがダブルに比べてシンプルに見えるので格式が低く見えたりするので年配の方のみが着用するイメージになったのかもしれません。好みや時代の流れにもよりますが購入される方は昨今ではほとんどがシングルスーツを購入されています。 |
昨今では葬儀に参列されている方のほとんどは準喪服を着用しています。ネクタイを付け替えれば冠婚葬祭の両方で着用できますので大変便利なスーツになります。

| 略礼装(略喪服) |
| 黒系や濃紺・濃いグレーなど地味な色合いのダークスーツに白のYシャツ・黒のネクタイが略喪服にあたります。急な訃報を聞き、準喪服が準備出来ない場合に通夜式や告別式・ご自宅などに駆けつける際に着用します。地味目であればストライプ柄のスーツや色の付いたネクタイでもよいでしょう。 |

| 和装(正喪服) |
| 男性の和装では1番格式が上の和装になり、黒羽二重染め抜きの五つ紋付き羽織袴姿になります。半襟や長襦袢は白や黒・グレーを着用し角帯は地味な色合いのものを巻き、白足袋に黒の草履が一般的で扇子は持ちません。家族葬では男性の着物姿はほとんど見られなくなっており、洋装が9割以上を占めています。 |
装飾品・アクセサリーについて
| ネクタイ | 黒の無地が基本となりネクタイピンは付けません。個性的な結び方は避けスタンダードな結びにしましょう。ディンプル(くぼみ)を作るくらいならよいかと思いますが、あえて付ける必要はないといえます。 |
| ワイシャツ | 柄のない無地で白シャツが基本となりますが、急な訃報で駆けつける場合は無地でなくても構いません。その際は地味目な色合いを選びましょう。 |
| 靴 | 黒の紐靴が正式な靴となります。金具や装飾などがついたデザイン性のあるものや、茶系など色のついたもの・ヘビやクロコダイル型押しなどのものは極力控えるのがマナーです。 |
| 時計 | 時計は付けててもマナー違反とはなりませんが、派手な時計(ゴールドやコンビなど)や高級な時計はあえて付けていく必要はないといえます。アップルウォッチなどのスマートウォッチは問題ありません。 |
| ピアス | ピアスは外していくのがマナーといえます。年配の方が参列されることが多いので、よくは思われないでしょう。 |
子供の服装について

| 小学生・中学生・高校生 |
| 学校指定の制服があれば、制服が正式礼装となります。制服が無い場合は黒や濃紺などの地味な色合いの服装を選びましょう。赤ちゃんの場合は極力装飾がない地味な服を着せてあげましょう。大学生ともなれば一般的には大人となるため、喪服を準備されるのが望ましいです。 |

2022.01.23
葬儀参列の靴の種類や色・素材や靴下【男性・女性・子供】|フォーマルシューズについて
はじめに 急な葬儀に参列する際履いていく靴が無い・・・。 どれを履いて行けばいいのか・・・? 時間はあるし購入しようかな? 靴下はどんな...
弔事・仏事においてその他のマナー
| 携帯電話 | 式中式場での使用を控え、マナーモードもしくは電源を切っておきましょう。台風の時期など災害の警報が鳴ることがありますが、こちらが鳴ってしまうのは仕方がないことといえます。 |
| ハンカチ | 色物や柄物は極力避け、地味な色合いのものを持参しましょう。 |
| 傘 | 赤や黄色など目立つ色を避け地味目な色合いのものを選びましょう。 |
| 香水 | 故人様を偲ぶ場所でありますので強い香りを避けるのが一般的です。 |
| 数珠 | お数珠を忘れて参列する方が多いので、お持ちであれば持参しましょう。ご用意出来ない場合はご親戚にお借りするか、葬儀社に言えば数珠を貸してくれます。 |
| お子様 | 小さいお子様はどうしてもお葬式を怖がります。普段よく使われてる音のならない小さいオモチャなどをお持ちされるのもよいかと思います。 |
喪服は購入とレンタル(貸衣装)ではどちらがいい?
家族葬の増加に伴い、「家族葬だから服装にそこまでこだわらなくいていい」と言う声や考えもあったりします。
そして、お葬式に頻繁に参列されるという方はあまりいらっしゃらなく、「いつあるか分からない葬儀のために喪服を購入するのは悩む・・・」という方も多いのではないでしょうか?
喪服を持っていない場合に葬儀参列のシーンがきたらレンタル(貸衣装)がよいのか?購入したほうがよいのか?服装にこだわらずダークスーツ(略喪服)で参列するか?で迷いますよね。お子様や学生さんは制服があれば正式な服装となるのですが、社会人になると一着は用意しておきたいものです。
こちらでは喪服の購入やレンタルする際のメリット・デメリットを紹介いたします。
喪服購入のメリット・デメリット
| メリット |
| メリットは、もしもの時に服装に困らないことです。お葬式はいつあるか分からなく、大半は急な訃報を聞いて、急に参列する場合が多いです。喪服やダークスーツなどがあればいいのですが、持っていない場合は地味目な色合いの普段着で参列することになり、浮いてしまうので少し恥ずかしいという声を良く聞きます。仕事中や用事がある際、急な訃報を聞いてから準備するのは難しい場合が多いです。お葬式の参列は滅多にないとはゆえ、訃報の際、困らないことがメリットだといえます。また、事前に調べて購入出来ますので比較的リーズナブルな費用で、経済的負担も抑える事ができます。 |
| デメリット |
| デメリットは費用や体型による問題になります。年齢などにより体系が変化する方が多く、若い時に購入した服は年を重ねるとサイズが合わない場合が多くなり、買い直しの可能性も出てきます。レンタル(貸衣装)よりも費用が掛かってまいりますので、喪服を頻繁に着用しない方はレンタルの方がよいのかもしれません。 |
喪服レンタルのメリット・デメリット
| メリット |
| レンタルのメリットは購入するよりも費用が抑えることができ、体型につきましてもサイズを気にする必要はありません。特に体系の変化により買い直す必要がないため、頻繁に喪服を着用されない場合はレンタルがおすすめといえるでしょう。 |
| デメリット |
| デメリットは貸衣装屋さんでサイズが無かった場合、オーバーサイズで浮いてしまうことや、貸衣装屋さんが定休日で何件も問い合わせないといけなくなったり、最悪の場合レンタル出来くて準備ができないことです。また、喪服を着用する機会が多い場合は購入した方が安く済みます。 |
結局どちらがいい?
それぞれのメリット・デメリットをご紹介させて頂きましたが、費用の面でいうとレンタルかと思いがちです。しかし昨今では、スーツや喪服においても品質の差はありますが安価なものが販売されており、コストパフォーマンスの高いユニクロさんやしまむらさんでも喪服が販売されていたりもします。数回着用すると元は取れるのでレンタルと購入では費用面で極端な差はないかもしれません。
家族だけの葬儀であればダークスーツ(略喪服)でもいいと思いますが、準喪服(ブラックスーツ)以上の喪服を着用してお葬式に参列しないといけないシーンがあるかも知れませんので、大人のマナーや心構えでいうと購入がおすすめといえるでしょう。
まとめ
こちらでは喪服のマナーや購入とレンタルではどちらがいいのかをご紹介しました。
喪服には「略喪服」「準喪服」「正喪服」の3種類があり、着用する方の立場や弔事のシーンによって異なるということがお分かりになったかと存じます。
そして、購入とレンタルでは一時的にはレンタルの方がいいのですが、長い目を見ると購入する方が断然よいです。
お葬式での喪服のマナーや靴・装飾品などのマナーについては皆様からよくご質問があります。
世間一般的に、そして昔ながらの正しいマナーがございますが、人の死は突然訪れますので急に喪服を準備することが難しいケースも多かったりします。
しかし、大人のマナーとして1着喪服を所持していてもよいというのが私の考えです。
装飾品・アクセサリーにおいて葬儀場はファッションをする場では無いので、あえて目立つ装いをするというのは好ましくありません。葬儀場は故人を偲ぶ神聖な場となりますので控え目を心がて装いをして頂くのがよいといえます。
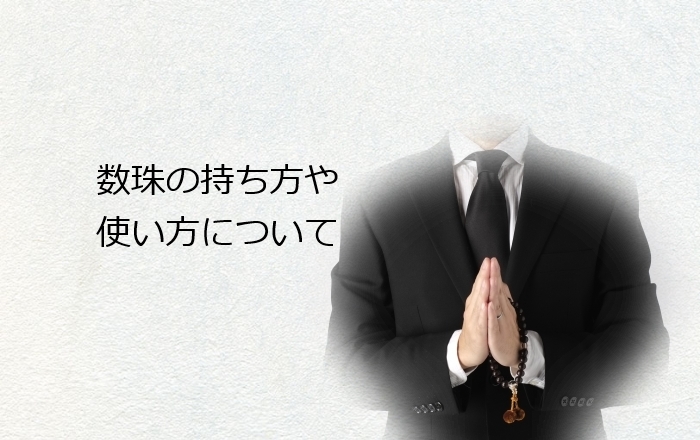
2021.04.30
【葬儀のマナー】宗教・宗派ごとの数珠の持ち方や使い方について
はじめに お葬式に参列し、いざ焼香の順番が回ってきたらお数珠の持ち方が分からず戸惑う方は多くいらっしゃいます。 通常は皆様に背を向けての焼香...
公開日 2023年9月19日|最終更新日 2023年9月19日