【2024年版】家族葬・自宅葬専門フローリー| 直葬・一日葬・二日葬・自宅葬儀に対応。

直葬プラン93,500円(税込)
【2024年版】家族葬・自宅葬専門フローリー| 直葬・一日葬・二日葬・自宅葬儀に対応。
目次
香典という言葉は誰でも聞いたことがあるかと存じます。
お葬式で遺族に対し現金を白い封筒に入れお渡しする儀式です。
しかし、「いくら入れればいいの?金額相場は?」「お金の入れ方は?」「書き方は?」「香奠の意味は?」など、さまざまな疑問点を持っている方も多いはずです。
こちらでは香典のマナーについて詳しく解説していきます。
読み方は「こうでん」となり「香奠」と書くことも一般的で、どちらも同じ読み方であり同じ意味で使用されます。「奠」という漢字には「供える・供え物」という意味合いがありますので、本来であれば「香奠=お香(線香)を供える」という意味になります。
昨今では「香典」と記述することも一般的ですが、「典」と「奠」の使い分けの違いは特にはありません。「奠」という漢字が難しく常用漢字ではありませんので「典」という漢字が普及していきました。
本来はお香を供える意味になりますが、いつから現金を供えられるようになったかというのにはさまざまな説があり、元々(室町時代~江戸時代)は一般的に米や野菜などの食べ物を供えられていたようで、現金を供えるのはごく一部だったといわれています。
今でこそ安価なお線香やお香が売られていますが、香木(こうぼく)を100%使用したお香は今でも非常に高価なものになりますので、その代わりになる食べ物を香奠としてお供えされていたといわれています。
安価なお香やお線香が普及し始め、お香をお供えされるようになったようですが、経済の成長とともにお香より現金を包む方が実用的であるということから現在の形になっていったとされています。

香典を入れる袋のことを「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」または「香典袋(こうでんぶくろ)」といいます。
結び目の部分を「水引」といいますが、「白色×黒色」が一般的で多く使用されており、水引の結び方などにも意味があったりします。
»水引について詳しく知る
宗教・宗旨・宗派問わず白×黒が一般的ですが銀×黒でも構いません。神式(神道)の御玉串料の場合双銀(銀×銀)や双白(白×白)の水引が付いたものを使用したり、キリスト教では十字架やユリの花のデザインがあるものを使用したりする場合もあります。

お祝いなどの祝儀袋やのし紙についている黒丸の部分を「のし(熨斗)」といいますが、弔事(葬儀や法要)などでは付けないことが常識となります。
お店で売っている香典袋はのしが付いていませんので心配する必要はありません。

香典袋には一枚の封筒のものと、外袋・中袋が付いているタイプがあります。水引がプリントの香典袋であれば直接現金を入れる封筒になり、水引が結ばれているものであれば中袋が付いていたりします。
不祝儀袋の表で水引の上に御香奠・御玉串料・御献花料・御霊前・御仏前など書かれている部分を「表書き(おもてがき)」といいます。
宗教によって書き方などがありますが、参列する際に相手方の宗教が分からないというケースの方が多いかと思います。
相手方の宗教や宗派が分かる場合については、
| 御香奠 | 上記で説明した通りお香を供えるという意味合いがあることから、仏式のお葬式での書き方になります。しかし、香典という言葉は宗教・宗派問わず一般的に使用されていますので幅広く使用できる表書きになります。 |
| 御霊前 | こちらも幅広く使用できますので、相手方の宗旨が分からない場合には御霊前で対応できます。ただし、浄土真宗では「霊」という考えがないため、あまり使用しません。 |
| 御仏前 | 仏教の浄土真宗のお葬式ではこちらを記述します。四十九日法要以降の法要では他の宗派でも使用します。「御佛前」と「御仏前」は旧字体か新字体になりますので、どちらでも問題はございません。 |
| 御玉串料 | 玉串は榊であり、主に神式のお葬式で使用します。「御榊料」や「御神前」と記入されても問題ございません。 |
| 御花料 | キリスト教のお葬式で使用します。「御献花料」と記入されても問題ございません。キリスト教では焼香よりも献花を行うケースが多いためお花代の代わりにこのように記述します。 »献花(けんか)とは? |
葬儀に参列する際に遺族の宗教や宗旨に合わせて書きますが、相手方の宗教が分からない場合は「御香奠(御香典)」「御霊前(ごれいぜん)」と書いておけば問題ありません。

水引の下に名前を記入しますが、苗字だけや〇〇家と記入するよりフルネームでの記入が丁寧になります。フルネームで記入する場合は代表者(主人)の名前を記入しましょう。
※代表者が女性であっても問題はございません。

「裏書(うらがき)」とは香典袋の裏に記述する部分になります。
裏書きに記述する事項は、
| 外袋・中袋付 | 水引が結ばれており中に別の袋(中袋)が入っている場合は、中袋に裏書を記述し表書きは外の袋にのみ記述します。中袋の表側の中央に金額を記述しても問題ありません。 |
| プリントタイプ | 水引がプリントタイプのもので中袋がないタイプのものには、裏書も表書きもその袋に記述しましょう。金額の記述は裏側にのみ記述します。 |
名前は表に記述するため記入しなくてもよいです。郵便番号や住所・電話番号につきましては記述しておく方が丁寧ではありますが、親戚や友人・知人など記述する必要が無い場合は省略しても構いません。
葬儀参列の際に受付でこのあたりは記帳しますが、金額の記述は遺族も確認しやすいので書いておく方がよいといえます。
筆ペンには通常のタイプと弔事用の薄墨タイプの2種類があります。
香奠(香典)やご霊前などはお供えや宗教者へのお礼とは違いお悔やみとなりますので、濃い墨ではなく薄墨の筆ペンなどを使用するのがマナーとなります。
理由としては悲しみの涙で墨が薄まってしまったといういわれがあるからです。

葬儀後の法要で現金をお供えする場合は、一般的には49日までは薄墨を使用します。薄墨を使用する期間というのに決まりはありませんが、49日が経つと忌明けとなり遺族やご自身も悲しみが少し落ち着くからです。
現金を包む場合は裏側に金額を記述しておくと遺族は分かりやすいです。
水引は「黄×白」のものは主に関西地方でよく使用されておりますが、「黒×白」「銀×銀」「白×白」などを使用しても問題ありませんが、「白×白」は神式の場合に使用することが多いです。また、表書きは「御供」「御佛前」「御霊前」などが一般的で、浄土真宗の場合は「御霊前」ではなく「御佛前」となりますが「御供」でも問題ありません。
表書きが「御供」なら、どの場面・宗教の法要でも幅広く使用できます。

お札につきましては新札を使わないのが香典のマナーとなります。古札でもあまりにシワが寄っているものは避け、比較的綺麗な古札を使用しましょう。手元に新札しかない場合は、半分で折り目を付けるなどして入れるようにするのがよいといえます。
理由としては、通常はピン札を入れて相手側に渡すことがマナーですが香典の場合はお祝い事などとは違い、前もって銀行で新札を準備するものではなく、新札の使用は事前に訃報を予測しているとも取れるからです。
しかし、昨今ではそこまで気にしない方も多くいたり、新札に折り目を付けた所で折り目が付いた新札程度にしかなりませんので、財布に古札が無ければ新札に折り目を付けるだけでも問題ありません。

現金が入っているため糊付けが必要と思っている方も多いと思いますが、中袋が付いているタイプ・付いていない簡易な不祝儀袋(祝儀袋)のどちらも、糊での付着は必要ありません。
ご遺族や受付の方が香典を受け取った際、中身を確認しづらく時間を要する可能性があるからです。しかし、中袋が付いていないプリントタイプの香典袋の場合、もしお金が袋から落ちたりする心配があれば糊付けをしても問題はありません。。
不祝儀袋(祝儀袋)や封筒の裏側に「〆(しめ)」「緘(かん)」「封(ふう)」という文字が記入されているのを見たことがあると思います。
これらは封字(ふうじ)と呼ばれていて、糊付けを行った上で文字を記入するもので、一般的に本人(受取人)のみ、もしくは確認してもらいたい方だけに送付する大切な書類などに記入する文字となり、御布施や香奠・祝儀などでは封字を記入する必要はありません。
また、不祝儀袋に手紙などを添えて本人やご遺族に渡す場合も封字は使用しません。市販の不祝儀袋(祝儀袋)には封字のシールが付属されているものもありますが、こちらも貼ってとじる必要はありません。「〆」と「×(ばつ)」や「メ(め)」は文字も意味も全く異なりますのでご注意を。
封字にはさまざまな種類や、それぞれに使い分けがあります。
|
香奠の相場は故人様やご遺族との関係が濃ければ濃い程金額が高くなってまいります。
友人や知人・会社関係の方であれば金額が低く、ご親戚であれば高くなるのが一般的です。あくまで平均値ですが低くて3,000円から高くて100,000円くらいが一般的となります。
昨今では家族葬の増加に伴い、香典辞退が非常に多くなっていたり、年齢層が若くなっていたりしますので、香典の儀式という風習や文化が薄れて来ているのが現実です。
| 自分の両親 | 5万円~10万円 |
| 配偶者の両親 | 5万円~10万円 |
| 祖父母 | 1万円~3万円 |
| 配偶者の祖父母 | 1万円~3万円 |
| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |
| 配偶者の兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |
| その他のご親戚 | 1万円~3万円 |
| 会社の上司 | 5千円~1万円 |
| 会社の同僚 | 5千円~1万円 |
| 会社の部下 | 5千円~1万円 |
| 友人・知人 | 5千円~1万円 |
こちらはあくまで目安・平均値になります。過去に香典を頂いたりした場合はそちらに合わせたり、周りの親戚や友人・知人などに相談して金額をご自身で決めて下さい。また、4や9という数字は死や苦しみの忌み合いがありますので避けておきましょう。お札につきましては新札を使わないのがマナーとなり、古札でもあまりにシワが寄っているものは避け、比較的綺麗な古札を使用しましょう。手元に新札しかない場合は半分で折り目を付けるなどして入れるようにするのがよいでしょう。
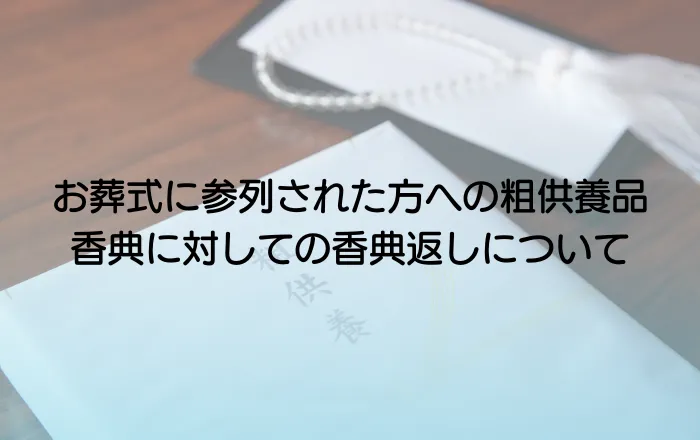
2024.02.27
通夜・葬儀の粗供養品や香典をいただいた場合の香典返しについて お通夜式と葬儀告別式に参列していただいた方に対して「粗供養品」をお返し...
香典は袱紗(ふくさ)と呼ばれるものに包んで渡すのが一番丁寧なお作法ですが、急な訃報で準備ができない場合はそのまま渡しても問題はございません。
»袱紗(ふくさ)についてはこちら
葬儀場の受付で渡す場合や遺族に直接渡すケースもありますが、「この度は誠にご愁傷さまです。謹んでお悔やみを申し上げます。」など一言添えると丁寧で礼儀正しい印象をもってもらえます。
香典袋の文字が相手側から正しく見える方向に向け、両手を添えて渡しましょう。
葬儀はいつ訪れるか分かりませんが、香典袋はどこでも売っていますのですぐに準備できます。
など、近くのお店での購入がよいといえます。
100均の香典袋は失礼かな?とい疑問があると思いますが、割としっかりとできており誰も100均だとは気づきませんので全く問題はないです。100均だからといってものが安っぽいということもありませんから。
こちらでは香典(香奠)の意味や書き方・入れ方・金額相場などのマナーについてご紹介いたしました。
表書きや裏書の記述方法、お金の入れ方、金額の相場など一般的なマナーはお分かりいただけたかと存じます。
昨今では香典を辞退されているお葬式がほとんどですが、もしもの時のために正しいマナーを知っておきましょう。
一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
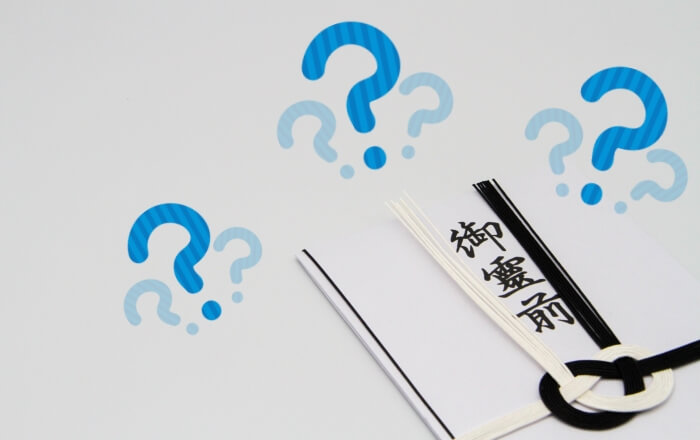
2023.07.18
はじめに 昨今では香典を辞退されるケースが増えていますが、それでも香典を受け付けるケースの葬儀もまだあります。 そんな中、という事例がご...
公開日 2023年7月15日|最終更新日 2024年2月28日