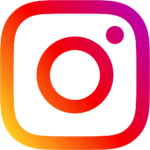渦巻き線香について解説いたします。

左側が一般的に使われる1本線香で、右側が渦巻き線香です。渦を巻いている形状から渦巻き線香と呼ばれていますが、業界では略して巻き線香(まきせんこう)と呼んでいます。
葬儀の際にお線香を手向けるのは一般的であり、皆様にも葬儀=お線香というイメージがあると思います。また、葬儀の間や49日の間、線香を絶やしてはいけないという云われも聞いたことがあるのではないでしょうか。
仏事においてなじみ深いお線香ではありますが、こちらでは巻き線香についての知識やいつまでつけるのか?などについて解説したいと思います。
渦巻線香について
一般的な1本線香の略式が渦巻線香となります。燃焼時間が1本線香に比べて長くなり1本線香で約40分程度、渦巻線香で約8~10時間程度燃焼します。
なぜ渦巻線香が普及したのかというと、葬儀の際「寝ずの番=24時間線香を絶やしてはいけない」という風習が昔からあり、遺族や親戚で交代しながら夜通しお線香のもりをしていましたが、昨今ではその風習も薄れつつあったり見れない
- 遺族、親戚が少ないため24時間火の元をみれない。
- 寝不足で心身共に疲労し葬儀に支障が出る。
- 火の元が心配。
- お線香の匂いが苦手。
- 家がお線香くさくなる。
などなど、さまざまな理由により葬儀だけに関わらず線香を焚く文化も昔に比べると減ってきています。
しかし、葬儀の際はお線香を絶やさない方がいいという考えが多いことから、1本線香では頻繁に取り換えないといけないけど、渦巻線香であれば長持ちする!という考えから誕生したものとみられます。
| 線香を絶やさない理由としては、線香の煙がお浄土への道しるべとなる、仏様がお香の香りが大好きなどなどさまざまな考え方があったりします。 |
似たようなもので渦巻型の蚊取り線香がありますが、明治28年(1895年)にキンチョール(金鳥)でおなじみの「大日本除虫菊株式会社」から販売されておりますので蚊取り線香をモチーフとし作成されたとされています。
蚊取り線香との違いについて

形状は似ていますが使われている成分が異なります。蚊取り線香は虫をやっつける成分が含まれており匂いも独特ですが、渦巻線香は仏事で使用する香木や香料などが含まれた1本線香を長くし渦巻状にしたものです。見た目は似ていますが蚊取り線香は横に太く、渦巻線香は細い形状になっているのが特徴です。
| ※成分や匂いが異なりますのでどちらも代用などはできません。 |
使い方・置き方について
葬儀社では渦巻線香専用の下皿も付いていますが、市販のものであれば下皿を別途購入しなければなりません。下皿に線香を置くための部品が付属していますので、そちらに置くか引っ掛けて使用します。あとはお好きなタイミングで火を付ければOKです。
どこで買えばいい?
仏壇屋さんで購入するのが無難です。さまざまな匂いのタイプが販売されており品物自体もそこそこの商品です。もしくはホームセンターでも販売していますし100均でも売っていたりします。
100均の渦巻線香の質は悪いのか・・・?については、その通りだと感じました。実際に購入して焚いてみましたが、煙が多いのと匂いがあまりよくないと感じました。
安いので当たり前ですが、仏壇屋さんや葬儀社で置いているものは基本的に煙が少なく匂いもいい香りがするものですので、そちらで購入することをオススメします。
渦巻き線香はいつまで使用する?

基本的にはご自宅もしく葬儀会館にご遺体を安置してから葬儀が終わるまでの間に使用します。ご遺体を安置し枕元に飾りつけ(枕飾り)を行うのですが葬儀社が1本線香と渦巻線香の2種類を準備してくれます。
上記であるようにお線香の説明を受けますので、どちらを使用するかはお客様次第です。本来では1本線香でみてあげるのがいいのですが、体調面であったり特にホール安置では着替えや準備のために自宅に帰らないといけませんので葬儀社スタッフは渦巻線香をススメてくると思います。
24時間付けっぱなし!?
渦巻き線香であれ火の元になります。お線香で引火して火事になるというニュースは見かけないのですが少し不安要素でもありますし、お線香の匂いが苦手な方やせき込む方も多く、電気式のローソクや線香で対応する方が多かったりします。
寝ずの番という言葉があることから本来であれば故人様に付き添い線香を絶やさない方がいいのですが、昨今では電気式の便利なものが販売されていますので利用されてもよいといえます。
四十九日までは使用すべき?
葬儀が終わり四十九日法要までの間は渦巻線香は基本的には使用しないことが多いです。渦巻線香は寝ずの番で便利に使用できるものであり、葬儀後は1本線香で故人を偲んであげましょう。
家庭環境によって状況が大きく異なりますが、
- 朝起きたとき
- おやすみの前
- 故人をふと思い出したとき
などなど、生活に支障のない程度でお線香を立ててあげて下さい。
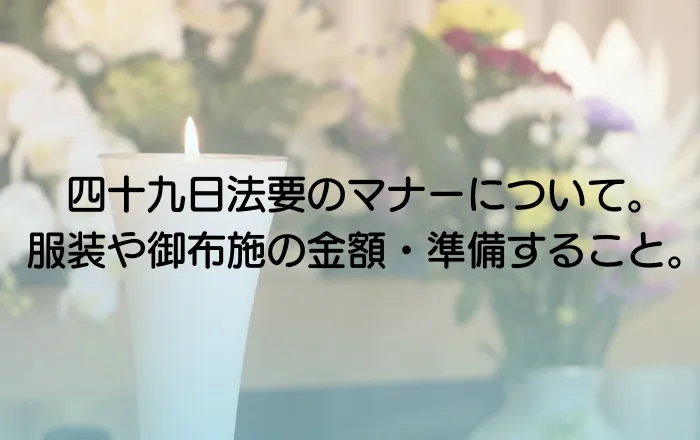
2024.02.27
四十九日法要とは?法事のマナーや服装・御布施について解説します。
四十九日法要について 葬儀が終わったあとの仏事において「四十九日(しじゅうくにち)」という言葉を聞いた事があること思います。 四十九日は亡く...
参列者は1本線香で!
自宅や葬儀会館に参列する方は1本線香を立ててあげます。遺族も弔問に来られた方に対しては1本線香で対応してあげましょう。
渦巻き線香使用にあたっての注意点
渦巻き線香のメリットは心身の負担を軽減できることですが、デメリットというか注意点といたしましては他の親戚(特に年配の方)に「手を抜いてはいけない」などと指摘される可能性があるかもしれません。
また、お坊さんに「あまりよくない」と指摘される可能性もあります。こちらは実際に枕経にお坊さんが来られた際、遺族に指摘していたのを見かけたことがあります。
しかし、昨今ではこのような指摘を行う方は稀であり非常に少ないので、そこまで心配はしなくてもよいです。
火事になったりしない!?
1本線香や渦巻線香が原因での火災は稀なようですが、ローソクには特に気を付けましょう。ローソクは炎が灯っていますので近くに燃えやすいもの「カーテン」「紙類」などがある場合はすぐに燃え広がります。
お線香での火事は少ないといえど、
旧田中角栄元首相邸が全焼 1階の仏壇付近から出火か
警視庁などは、仏壇の線香の火から燃え広がった可能性があるとみて出火原因の特定を進めています。
引用元:NHKニュース
とありますので、どちらにせよ火の元から決して離れないことが家事を防ぐ唯一の方法です。また、ペットを飼っている場合は仏壇や飾り段の近くに近寄らないようにしておきましょう。
お線香の煙で匂いが充満してむせたり、部屋の壁紙が黄ばんだりする可能性もありますので換気することも大切です。
火災予防には電気式がオススメ!

火の元が心配な方は電気式のローソクやお線香がオススメです。仏壇屋さん・ホームセンター・100均などで購入可能です。遺族がホールにいない場合など葬儀社でも使用されているものとなります。
外出する時やおやすみになる時は電気式が安全で安心です。
渦巻き線香まとめ
渦巻線香は通常のお線香を長くしたものを渦巻状にし、長時間灯せるものとなり非常に便利です。
お通夜の際に楽にお線香をたやさないためのアイテムですが、稀に親戚やお坊さんに指摘される可能性もあるということを頭に置いておきましょう。
しかし、体調を崩さないためにもこちらを使用される方が非常に多く、1本線香と上手く使い分けることがよいといえます。
また、お線香をたむけることは故人様への供養となる重要な儀式ですが、火事に繋がる可能性も稀にありますので線香やローソクを点ける際は火の元から目を離さないことが大切だといえます。
一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
公開日 2024年6月19日|最終更新日 2024年6月19日