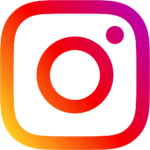目次
友引と葬儀は本来関係がない!
友引に葬儀を行ってはいけないという話はをご存じですよね。葬儀と友引が重なった場合、日時を延期しようとする方はたくさんいらっしゃり、日本日本において友引にお通夜式や葬儀告別式を行ってはいけないという意識や風潮が強く根付いています。
しかし、結論からいうと友引に葬儀をしてはいけないという決まりなどは全くなく、お葬式を行っても問題はございません。ただの迷信になります。
こちらでは友引の意味や葬儀を行ってはダメといわれる理由・葬儀との関連性などについてご紹介いたします。
そもそも友引とはどんな日なの?
友引=「ともびき」と読みます。
友引は中国で生まれた考え方で、その日の吉凶などの運勢を表す「六曜(ろくよう」といわれる※暦注になります。カレンダーに記載されている先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口が六曜にあたり、それぞれの日や時間に縁起の良し悪しなどの意味があります。
| ※暦注(れきちゅう)とは、暦によって運勢や方角の吉凶を表す占いのようなものです。友引は方角は関係ありませんが恵方巻はその恵方(縁起がいい方向)を向いて巻寿司を食べますよね。ウナギを食べる「土用丑の日」も暦注の一つにあたります。 |
もともと六曜と仏教や葬儀には何の関連性も無かったのですが、いつの日にか日本全国の文化や風潮にに浸透し、「この日は仏滅だから〇〇は辞めておこう」「大安だから〇〇しよう」というように、行事を行う日を六曜によって決めるということがよくあります。
六曜のそれぞれの意味や考え方はこちらです。
| 先勝 | 「さきがち・せんしょう」と読みます。先手を打つことが良いとされる日で、午前中を吉・午後を凶とする考えです。 |
| 友引 | 勝負が付かなく良くも悪くもない「共引き」とされる日です。朝と夜は吉とされ、午前11時から午後1時の時間帯は凶とされる日です。 |
| 先負 | 「さきまけ・せんぶ」と読みます。急いで行動をすると負けてしまうという意味で、午前中を凶・午後を凶吉とする考えです。落ち着いてことを進めるのがよいてされます。 |
| 仏滅 | 「ぶつめつ」と読み、六曜の中で最も凶日とされる日です。仏様が滅するほど悪い日。結婚式などお祝い事を避ける場合が多いです。物滅から仏滅になったとされる言われもあります。 |
| 大安 | 「たいあん」と読み、六曜で最も吉日とされる日です。結婚式や結納などお祝い事を大安に合わせて行う場合が多いです。お祝い事に適してる日だからといって、お葬式を行わないなんてことはありません。 |
| 赤口 | 「しゃっこう」と読みます。午前11時ごろから午後1時ごろまでが吉で、それ以外は凶とされる日になります。赤とい色が火や血を連想させるため、怪我や事故にも注意する日と言われています。 |
六曜の意味と比較して見ると、友引と葬儀や仏教などとは関係性がないことが分かります。
ただ単に「友引」という漢字と読み方から友を引くという言い伝えや文化・迷信になったとされます。実際に友引にお通夜式や葬儀告別式を行って親戚や友人・知人が故人に引かれて亡くなったという話はほとんど聞きません。

2024.03.19
2024年(令和6年)の春と秋|お彼岸の意味や期間ついてご紹介します
お彼岸について詳しく解説 「彼岸(ひがん)」は誰もが聞いたことがある言葉だと思います。そして不吉で怖い期間というイメージを持たれている方...
なぜ友引に葬儀を避けるのか?
諸説がありますが友引という漢字を書きともびきという読みになることから「友を引く」すなわち、葬儀において友人や親戚を引き寄せる・あの世へ連れて行く(=亡くなる)というニュアンスがあるため葬儀では避けられる日になっています。しかし本来の意味合いではお葬式や仏教とは関係ありません。
友引の日に葬儀は非常識?ダメ?
友引に葬儀は避けたほうがいいのか?
友引に葬儀を行うことを非常識という方もいらっしゃれば仕方が無いと理解してくれる方もます。特に年配の方であれば昔からの風習なので友引に葬儀を行わないのが当たり前な考えであったりします。しかし仕事の関係や外せない予定がありやむを得ず友引に葬儀を行わないといけない場合もありますよね。
| 結論は友引という日は単なる迷信であり、本来葬儀とは関係ないので葬儀がダメな日ではありませんが、避けることができるなら日時をずらしたほうがよいです。 |
友引に葬儀を避けた方がいい理由
友引と葬儀の関係性はただの迷信なのですが、参列してくれる方の中には友引に対しての考え方を重視している方もたくさんいらっしゃいます。また、万が一参列者の方が亡くなってしまう可能性もゼロではないということです。友引に葬儀をすると誰かが死んでしまうというのには何の科学的根拠もありませんが、たまたま亡くなってしまうケースもあったりします。
人によっては「友引なんて気にしない」という考えの方も多くいらっしゃるのですが、特に年配の方が多く参列される場合や、体調が非常に悪い方が参列される場合では配慮は必要ということになります。
昨今では友引に対しての意識が薄まってきてはいますが、地域性や風習・年配の方などにはまだまだ強く根付いている考え方であったりします。
普段の生活において友引は「何気ない一日」でありますが、葬儀となると悪い日になってしまうのが現状です。葬儀社も打ち合わせの際はお客様に友引について説明したりします。
友引と葬儀の関係性を説明せずと施行してしまうと後々のクレームに繋がる可能性がありますので、葬儀社スタッフは友引カレンダーを常に携帯しており、この月は〇〇日が友引というのを頭に入れています。
友引に法事・法要はどうなの?
法事・法要は気にする必要はありません。友引はあくまで葬儀を避けた方がよい日であり、葬儀後は1週間ごとに法事を行いますし、参加される方の予定もあったりしますので法事・法要まで言い出したら切りがありません。
午後からの葬儀ならOK!?
お通夜が友引の場合は問題ないという考え、午後からの葬儀であれば問題ないという考えがあり、1時以降に葬儀を行ったりします。しかし、地域の風習や周りの方の意向を伺って日時を決めた方がよいといえます。
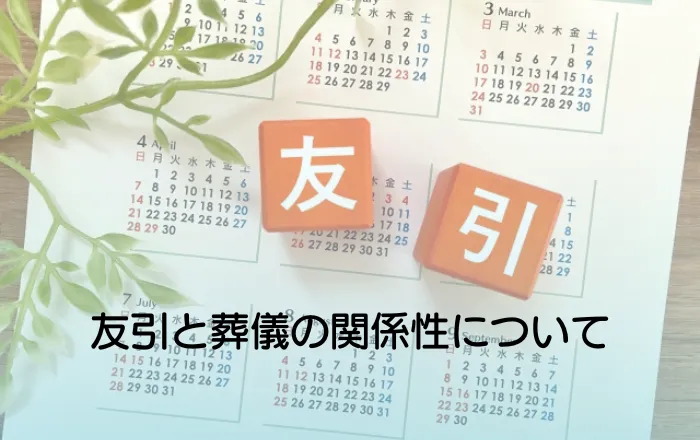
2023.11.29
実は友引と葬儀は関係ない!?お通夜と告別式がダメな理由について
友引と葬儀は本来関係がない! 友引に葬儀を行ってはいけないという話はをご存じですよね。葬儀と友引が重なった場合、日時を延期しようとする方はた...
実際に友達や親戚を引いてしまうのか?
何の根拠もありませんので、友引に友達や親戚が亡くなるというのは確率だけの問題でありジンクスですのでたまたまです。長く葬儀社に努めている方は実際に不幸があったというのは経験したことがあるでしょう。
友引を休館日としている火葬場(斎場)もあります
大阪など関西地方では友引であっても火葬場(斎場)の稼働はしていますが、関東やその他地域によっては友引に対しての意識が強く友引の日を休館日としている場所も多く火葬場が混む原因であったりします。
お通夜式は行えますが、葬儀は行えません。関東地方からの参列者に「友引でも火葬できるの?」と驚かれるケースがあったります。
友引人形というものが存在します。

地域によっては副葬品として「友引人形(友人形=ともにんぎょう)」といって、人形やコケシ・ぬいぐるみなどを納める風習があります。友人形をお棺に納めることにより友達や親戚を引く代わりに、人形が身代わりになってくれるという考えです。
葬儀社が用意してくれるケースが多いのですが、火葬場によっては納めることができない場合もあります。
友引が関係ない宗教・宗派もある?
仏教宗派それぞれの考えをご紹介します。
| 浄土真宗本願寺派(西) | 友引の葬儀は問題ない。迷信にとらわれてはいけない。 |
| 真宗大谷派(東) | ただの占いであり、葬儀を行っても問題ない。 |
| 浄土宗 | 火葬場が休館日だから葬儀を行えない・影響を受けるだけ。 |
| 真言宗 | 友引に葬儀を避ける風習にすぎない。 |
| 天台宗 | 友引に葬儀を行うことは悪くはないが、友を引いてしまう場合もあることから難しい。友引に葬儀を行ったから友達や親戚が亡くなったと考える人も少なからずいる。 |
ということにより本来友引と仏教は関係なく、葬儀がダメという理由はないというのが共通点です。しかし、火葬場が休みで行えない、たまたま引いてしまう可能性があるから「いいとはいえない」「難しい」ということも共通の考えであったりします。
| 真宗大谷派:高科 修 様 |
仏教以外の考え方は?
神道でも友引はただの迷信という考え方であり、キリスト教においても関係ないといわれています。
海外では友引を気にするのか?
海外では友引=友を引く概念はないようです。六曜発足の中国では9が付く日は非常におめでたい日であるため葬儀は行われないようです。
韓国本土でも六曜はあるようですが儒教形式で葬儀を行うため気にする人はほとんどいないようです。しかし韓国では、生まれた日によって良い日・悪い日のカレンダーのようなものや考え方があるようで悪い日には結婚式・お墓の建立・引越しなどは行わないといわれていますので、その日に葬儀を行わない方もいらっしゃるということでした。(※韓国人の住職に聞きました。)
以上のことから外国では友引だから葬儀を避けるという概念はないようです。しかし、帰化されて長年日本に住んでいる方などは日本の風習の影響もあり友引を意識する方も多いようです。
友引カレンダー
令和5年(2023年)
| 1月 | 6日・12日・18日・23日・29日 |
| 2月 | 4日・10日・16日・2026 |
| 3月 | 4日・10日・16日・22日・28日 |
| 4月 | 3日・9日・15日・25日 |
| 5月 | 1日・7日・13日・19日・24日・30日 |
| 6月 | 5日・11日・17日・21日・27日 |
| 7月 | 3日・9日・15日・20日・26日 |
| 8月 | 1日・7日・13日・17日・23日・29日 |
| 9月 | 4日・10日・15日・21日・27日 |
| 10月 | 3日・9日・20日・26日 |
| 11月 | 1日・7日・17日・23日・29日 |
| 12月 | 5日・11日・16日・22日・28日 |
令和6年(2024年)
| 1月 | 3日・9日・13日・19日・25日・31日 |
| 2月 | 6日・11日・17日・23日・29日 |
| 3月 | 6日・10日・16日・22日・28日 |
| 4月 | 3日・14日・20日・26日 |
| 5月 | 2日・12日・18日・24日・30日 |
| 6月 | 5日・9日・15日・21日・27日 |
| 7月 | 3日・8日・14日・20日・26日 |
| 8月 | 1日・5日・11日・17日・23日・29日 |
| 9月 | 3日・9日・15日・21日・27日 |
| 10月 | 8日・14日・20日・26日 |
| 11月 | 5日・11日・17日・23日・29日 |
| 12月 | 4日・10日・16日・22日・28日 |
友引と葬儀の関係性まとめ
こちらでは友引と葬儀の関係性を解説しましたが、仏教やその他宗派においても葬儀を行うことがダメではないことがお分かりいただけたかと思います。それならなぜお通夜と葬儀告別式がダメといわれるのか?
| 友引は友を引くと書くので友達や親戚をあの世に引くというニュアンスがある。 |
| たまたま友引に参列し、亡くなってしまう可能性もゼロではない。 |
| 古くからの風習なので年配の方が気にしたり、体調の悪い方がいい気がしない可能性がある。 |
という理由により、ダメというより可能であれば避けた方がいいということが結論です。
また地域によっては火葬場が休館日のところもありますので、葬儀を行えないケースもありますので良く確認をしておきましょう。しかし、仕事や予定がありどうしてもお通夜や葬儀を行わなければならない場合は仕方がないといえます。
万が一お葬式が友引と重なる可能性があるようなら周りの親戚に相談し、日時を決めることがよいでしょう。
一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
公開日 2023年11月29日|最終更新日 2023年11月29日