【2024年版】家族葬・自宅葬専門フローリー| 直葬・一日葬・二日葬・自宅葬儀に対応。

直葬プラン93,500円(税込)
【2024年版】家族葬・自宅葬専門フローリー| 直葬・一日葬・二日葬・自宅葬儀に対応。
本来の初七日法要は無くなられてから7日後に行う法事です。コチラで詳しく解説していますのでご覧ください。
式中初七日法要(しきちゅうしょなのかほうよう)とは、お坊さんが葬儀の読経を終えた後そのままの流れで行う形式で、年々増加傾向にあり需要が高まっています。
お骨上げの後ではなく例えば葬儀予定時刻が10時開式~11時出棺だとすれば、この1時間の間に葬儀告別式と初七日法要を行います。お骨上げ後に行う初七日法要を「繰り上げ初七日法要」といわれることから、「繰り込み初七日法要」とも呼ばれていたりします。
どの地域から始まり、誰が思いつき広まっていったのかは不明ですが、葬儀や仏事の簡素化は主に都心部から始まる傾向にあります。
式中初七日法要が出始めたのは最近で、家族葬の需要が高まった流れで出始めたイメージです。「式中初七日」という言葉は元々は存在せず、どこかの葬儀社が「これはいいんじゃないか・・・」というシンプルな考えで始まり、思ったより需要があるから自然と広まったといえるでしょう。
特に都心部において需要が高いのですが、理由としてはいくつかあります。
| 【時間の短縮】 一般的な繰り上げ初七日法要は骨上げ後に行うため葬儀の開式時間にもよりますが夕方までかかってしまいます。しかし式中であればお骨上げが終わると初七日も終了していますので、その時点で散会することができます。1日の予定が1時間~2時間程度短縮できます。 |
| 【高齢の方の負担軽減】 特に年配の方は葬儀から骨上げ、初七日法要までの参加となると心身の負担が大きくなります。その負担を少しでも軽減できることが需要増加要因の一つです。 |
| 【葬儀社目線】 葬儀社の目線で考えると会館や法事室が少しでも早く空くことから葬儀の回転率が若干上がったり心身の負担が軽減します。しかし葬儀社によっては初七日法要を骨上げ後に行うことで法事室の使用料が発生したりしますので、式中ではなく繰り上げの方がよいという考えもあったりします。 |
| 【寺院目線】 昨今では葬儀社からお坊さんを紹介してもらったり、インターネットで寺院を手配できる時代になっています。合わせて御布施の相場も下がっているのが現状です。お坊さんには「昔ながらを重んじる」「時代の流れに合わせる」という考え方の2パターンいらっしゃって、式中初七日法要を行ってくれないケースもあったりします。逆に御布施が低価格な分「式中の方が拘束時間が短いからよい・・・」と考えるお坊さんがいらっしゃるのも現実です。 
2023.10.07 坊主丸儲け?お寺さんは稼いでウハウハ?な噂話の実際と現状について坊主丸儲け? 「坊主丸儲け」という言葉を聞いたことがあると思いますが、意味はというと、 資本や資材などの元手が無くとも、仕事で大きな利益が出... |
1日の予定が短縮できることや年配の方への負担が軽減できること・初七日の法事室使用料が別途かかる場合は費用の削減がメリットですがデメリットもあります。
という意見もあれば、特に年配の方や寺院から反対されるケースも多くあったりします。
| 【年配の方の声】 昔ながらの本来の形式でずっと行っていたため「繰り上げ初七日法要はまだ理解できるが式中に行うなんて手を抜きすぎ」という考えがあります。 |
| 【寺院の声】 繰り上げで行うことは時代の流れであり一般的であるから理解はできる。しかし、遺骨もない式中に行うのは理解ができないし不精だ。また、それならしない方がマシであり、7日後に遺族や親戚だけで遺骨に手を合わせる方がよい。事情はいろいろあると思うが、故人のためのお葬式ということを考えてほしい。 |
などなど、当たり前な意見も多く他の親戚に「何故このような形式にしたのか?」と言われたり、寺院には断られるケースもあったりします。いくら葬儀が時代とともに簡素化されてるとはゆえ、他の親戚に相談したり寺院によく確認しておかなければなりません。
寺院によっては繰り上げ法要でさえも行わないケースもあります。
増加傾向にあり今後も現在より増加していくと感じてはいますが、一般的になるにはまだまだ先のように感じます。特に地方(田舎)では都心部より大幅に遅れて流行する傾向にあったり、風習を重んじる地域も多いため葬儀社も式中初七日を提案しなかったりもします。
一般的には葬儀式のお経(30分~40分程度)+初七日法要10分の合計40分~50分程度が所要時間です。限られた時間の中で法要を行いお別れをしますので初七日自体の時間はそこまで長くはありません。
中にはプラスアルファの時間を設けず、葬儀式のお経のみで初七日まで含むというやり方もあったりします。お坊さんの考えによりやり方や時間が変わってくるといえます。
| 本来の流れ | 繰り上げ初七日法要 | 式中初七日法要 |
| 告別式終了 出棺
精進揚げ
骨上げ
帰宅
七日後に初七日法要 | 告別式終了 出棺
精進揚げ
骨上げ
初七日法要
帰宅 | 告別式開式 初七日法要
出棺
精進揚げ
骨上げ
帰宅 |

2023.09.21
【記事監修】厚生労働省認定一級葬祭ディレクター/中原優仁はじめにご家族に不幸があった場合、落ち着いてスムーズに葬儀の手配を...
お葬式での御布施は「枕経」「通夜式」「告別式」「戒名料」「火葬炉前勤行」+「初七日法要」の合計になり、全て含めて20万円~30万円が相場といわれており、そのうち初七日法要のお礼は2万円~5万円程度になります。
寺院によって金額が決まっていたり、お気持ちでよいと言ってくれたりなどさまざまなので檀那寺がある場合は寺院に直接、葬儀社紹介であれば葬儀社に確認しておきましょう。
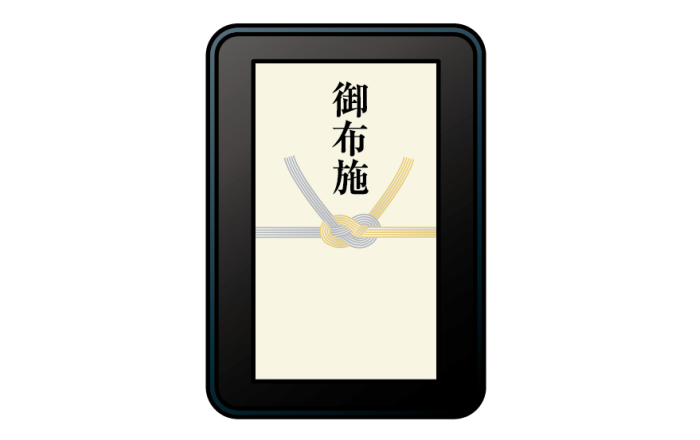
2023.07.15
御布施の意味について 御布施は葬儀にお寺さんが参ってくれた際にそのお礼として現金を渡すものになります。読み方は「おふせ」となり、「他人に...
こちらでは式中初七日法要の意味や流れ・メリットやデメリットに加え他の親戚や寺院の意見についてご紹介いたしました。
昨今では「一日葬」「お墓を建てずに永代供養(墓じまい)」など法要だけにかかわらず簡略化や価値観の低下・風習に対しての意識の薄れが進んでいます。
これからも葬儀や仏事の簡素化が進んでいくことが予想され、時代の流れということで仕方がないとはいえますが、故人様に対する感謝の意や供養をしてあげるということは形式に関わらず大切だといえます。
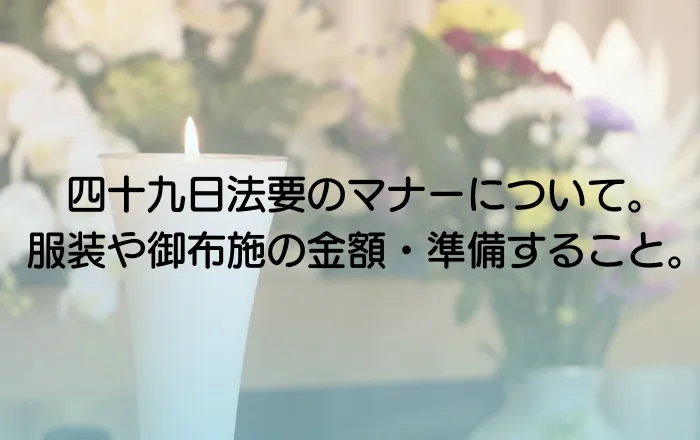
2024.02.27
四十九日法要について 葬儀が終わったあとの仏事において「四十九日(しじゅうくにち)」という言葉を聞いた事があること思います。 四十九日は亡く...
一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
公開日 2024年2月23日|最終更新日 2024年2月27日